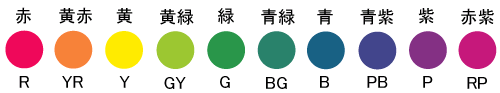
マンセルシステムは、アメリカの画家&美術教師であるマンセル(1858-1918)が、 1905年に考えた表色系です。顕色系のシステムです。 色相,明度,彩度の三属性で、色を記号化して表現しま す。日本でもJIS(日本工業規格)に採用され、産業界で広く用いられています。
現在、広く活用されているマンセルシステムの創始者 アルバート・マンセルは、アメリカの画家であり、美術教育者で ありました。彼はボストン出身で、マサチューセッツ美術学校で美術を 学んだ後、フランスに留学しました。フランスで研鑽を重ねて、高く評価され、 ローマに留学しました。その後に故郷ボストンに帰り、母校で色彩構成と 芸術解剖学の講師を担当し、1915年まで続きました。
彼が21才(1879年)のとき、当時評判がよかったO.ルードの「現在色彩学」を読んで、 彼の関心は絵画よりも色彩に向けられました。そして1905年にマンセルは、色彩球(色彩樹) として知られる色彩体系を考案しました。
彼の色彩球は、北極の位置が白で、南極の位置が黒であり、 赤道の位置には、各色相の中明度の有彩色が並んでいて、 北に行けば明るく、南にいけば暗くなっていくように考 えられました。これがマンセルの色彩体系化の試みで ありました。
1918年マンセルが世を去り、彼の友人や後継者たちがマンセル・カラー・ カンパニーを設立し、マンセルが目標とした「正確で客観的な 色の表示法の完成と普及」に努めました。
その後に1943年に、アメリカ光学会が、 マンセルシステムを改良しました。(どのように改良したか言うと ページがいくらあっても足りないんでカット)このシステムを 修正マンセルシステムと言い、現在マンセルシステムと言ったら、 このシステムを指します。
マンセルシステムは、「色相」「明度」「彩度」の三属性を用いて色を表現します。 マンセルは、明度は美術用語のバリュー(value)、彩度には絵画用語の クロマ(chroma)を使っています。色相は英語のヒュー(hue)を使い ます。
色相(hue)は、色相差が等間隔に見える主要な五種類の色相 「赤(R)、黄(Y)、緑(G)、青(B)、紫(P)」と、 五種類の中間の色「黄赤(YR)、黄緑(GY)、青緑(BG)、 青紫(PB)、赤紫(RP)」を決め、10種類の色相としました。
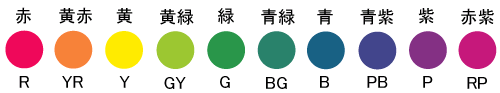
ちなみにどのように色相を決めたかは全くの謎です。ここで黄緑(GY)と青紫(PB) に注目すると、アルファベットと漢字の順序が逆になっています。色の検定で、 引っ掛け問題として出そうなので、注意が必要です。
10種類の色相が完成したら、各色相ごとに、0から10までの 目盛りを等間隔に振ります。(5の目盛りが真ん中になる) これによって100種類の色相が完成します。 (10色相×10目盛り=100)
色相が赤(R)の場合は、5Rは普通の赤だが、10Rは黄色っぽい赤、 1Rは紫っぽい赤になります。
下の図がマンセルの色相環です。通常は各色相の5と10を代表色とします。 (つまり色相環は20色相になる。)「マンセル色票集」や「JIS標準色票」 として発行されているものは、40色相になっています。各色相の「2.5」 「5」「7.5」「10」が色票化されています。(4×10=40)
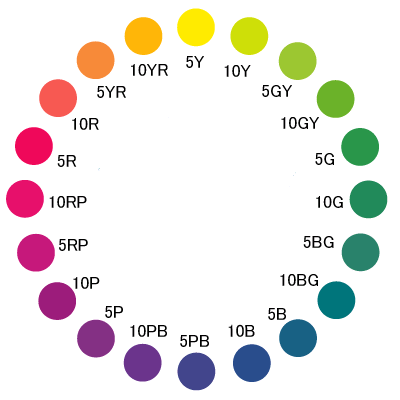
マンセル明度は0〜10の範囲で、理想の白を10とし、理想の黒を0とします。 しかし実際に色票にできるのは、1〜9.5までの範囲です。もちろん明度が高いと 明るい色になり、明度が小さいと暗い色になります。
彩度は色みの強さを指します。彩度の値が大きいと鮮やかな色になり、 値が小さいとくすんだ色になります。各色相において、もっとも彩度が 高い色を純色と呼びます。実際の色票(顔料)で表現できる彩度は、色相によって かなり違います。
有彩色の場合は、「H V/C」と書きます。たとえば鮮やかな赤なら、「5R 5/14」 と書きます。口頭でマンセル記号を言うときは、「5R 5の14」と読みます。無彩色 の場合、下のように明度で表します大文字のNをはじめにつけます。
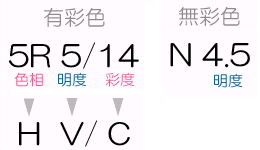 |
| SEO | [PR] おまとめローン 花 冷え性対策 坂本龍馬 | 動画掲示板 レンタルサーバー SEO | |
