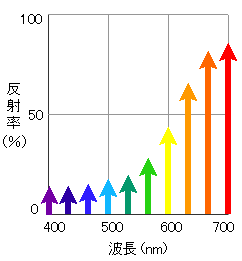
物体は「全ての波長の光」を様々な割合で反射し、 反射のしかたによって、見える色が決まります。 例えば赤の物体は長波長の光が多く反射している状態です。 横軸に波長を、縦軸に反射率をとると、下のようなグラフが になり、このグラフを反射率曲線といいます。反射率曲線は 分光分布とも呼ばれます。
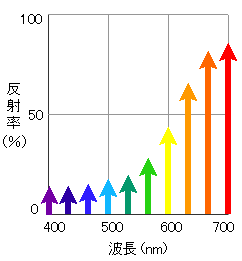
この曲線は赤い物体の例です。長波長の光が多く反射していて、 短波長の光はわずかにしか反射していません。裏を返すと、赤い物体は、 長波長の光を少しだけ吸収し、短波長の光をたくさん吸収してい ると言えます。上のグラフから、400nmの光(青紫の光)は、 10%ほどが反射され、90%ほどが吸収されていることが分かります。
反射率+吸収率=100%
反射率曲線とは、どの波長の光が、どのくらい反射しているかを 表すグラフなので、この曲線を見ると、大体の色が分かります。 この曲線によって、色を表すことが出来るのです。
このセクションでは、反射率曲線の形から、物体や光源が、 どんな色なのかを推測する手段を紹介します。またパソコンの カラー指定のテクニックも紹介します。反射率曲線と 色の三属性を知ると、パソコンで色を指定(RGB)するとき、 「どんな色を出したらいいんだろう。」と悩むことが、 少なくなります。
まずは色相から見て見ましょう。鮮やかな色を例にとって 説明します。色相は、どの波長にピークがあるかを見れば、 大体分かります。例えば長波長にピークがあれば、赤のような 暖色系ですし、短波長にピークがあれば青や青紫になります。
(A)は長波長にピークがあり、(B)は中波長にピークが あります。それぞれの色は、赤&緑と推定出来ます。
(C)は短波長側にピークがあるので、青色です。 (D)は長波長〜中波長とピークの幅が比較的広いです。赤の光と 緑の光が混ざると、黄色になります。そのため(D)は黄色であると 考えられます。
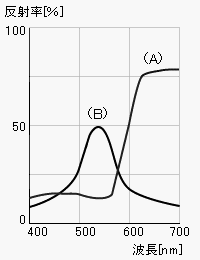
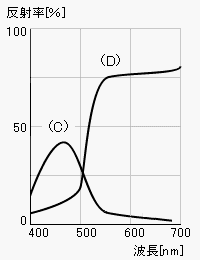
|
次のグラフはピークが二つあります。長波長側と短波長側 です。青と赤が混じって出来る色、答えは紫です。紫の反射率曲線 に比べて、長波長側の反射率が大きく、短波長側の反射率が 小さくなると、赤紫(マゼンタ)になります。紫や赤紫は スペクトルに存在しない色です。複数のスペクトルが混じ って出来る色なのです。
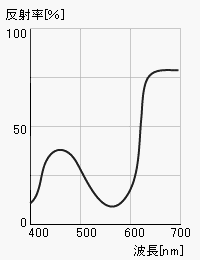
光が多く反射されれば物体は明るい色に見え、光がわずかにしか反射されないと 物体は暗い色に見えます。つまり色の明度は、光の反射量に依存するのです。
分かりやすいのが無彩色です。(左の図)反射率が高いほど明るくなり、反射率が低いほど 暗くなります。
右の図は有彩色の例です。(A)(B)共に中波長にピークがあるので、色相は緑であると 考えられます。しかし光の反射量は、(A)の方が(B)より多いです。従って 同じ緑色でも、(A)は「明るい緑」で、(B)は(A)に比べて「暗い緑」 なのです。
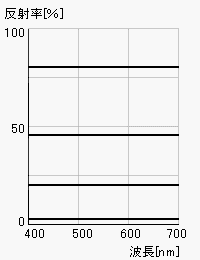
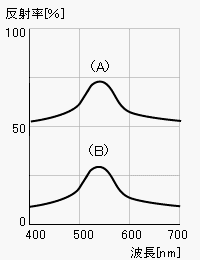
|
このように明度は、光の反射量に注目すると分かります。 反射率曲線と横軸に囲まれた面積が大きければ大きいほど、明度が 大きいと言えます。
無彩色は反射率曲線が平らです。逆に、特定の波長にピークがハッキリ表れていると、 その物体の色は彩度が高いことになります。特定の波長の光が、他の光より断然多く含 まれているからです。
反射率曲線の高低差が彩度を表しています。高低差が大きいほど鮮やかな色になり、 高低差が小さいほどくすんだ色になり、高低差がなくなると(平らになると)、無彩色 になります。
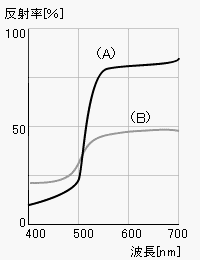
色の三属性と反射率曲線の知識があると、パソコンで 色を指定するとき、スムーズに出来ます。パソコンはRGB、すな わち「赤」「緑」「青」の三変数を0〜255の範囲で配分し、色 を指定します。
例えば鮮やかな赤の場合、緑と青は無視して、赤をたく さん配分すれば良いです。彩度は高低差を表すので「R=255 、G=0、B=0」が一番鮮やかな赤になります。
黄色は赤と緑の光が混ざって出来た色ですから、当然青は無視 です。オレンジは、赤と黄の中間の色なので、Gの値を下げます 。逆にRの値を下げると黄緑になります。
明度は反射量によって依存するので、R+G+Bの値 (光の量)が多ければ多いほど明るくなります。分かり やすいのが、無彩色です。
| SEO | [PR] おまとめローン 花 冷え性対策 坂本龍馬 | 動画掲示板 レンタルサーバー SEO | |
