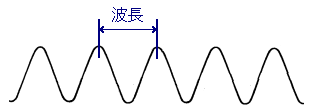
光が発生する源を光源といいます。光源の例として、 太陽、蛍光灯、白熱灯、水銀灯など様々な種類があります。 今回は視覚現象の三要素の一つである「光」について解 説します。
光は一種の電磁波です。電磁波には様々な種類があり、 赤外線や紫外線,可視光線(光)なども、電磁波の仲間です。 電磁波は波長によって様々な呼び名ががあります。波長とは、 下の図のように、山の頂点から次の山の 頂点までの長さを指します。
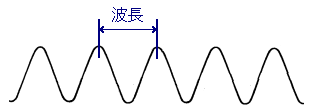
|
電磁波の中で、私たちの目に見える(色を感じれる)電磁波のことを、 可視光線と呼び、可視光線の波長の範囲は、だいたい380~780nmです。 全体で見れば、ごくごく限られた範囲です。
nmはナノメートルと呼び、1mの十億分の一の長さです。 地球の直径を1mと仮定すると、10億分の1メートルは、1円 玉の直径未満の長さです。「光」というと、普通は可視光線を 指します。ちなみに光の速さは約30万km/秒です。1秒間に地球七周半も するのです。
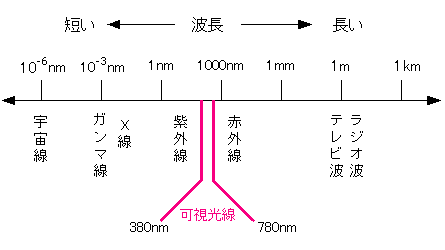
|
色みが感じられない光のことを「白色光」と言います。 太陽光は白色光です。輝く太陽の光。その中には美しい虹の色が 眠っています。太陽光をプリズム(透明な三角柱)に通すと、 様々な色の光が見えます。俗に言う「虹色」です。
白色光から、様々な色の光に分ける実験を、最初に行ったのがニュートンです。 彼は、暗い部屋の中に、小さな穴から太陽光線を導き、それをプリズムに通しました。 その結果、赤・橙・黄・緑・青・藍・青紫と変化していく色の帯が、スクリーンに映し出 されました。この色の帯のことをスペクトルと言います。
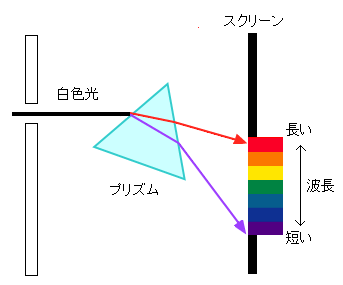
|
ニュートンの実験の結果、太陽光には、様々な色の光が含まれていること が分かりました。(この実験は「光学」に著されている。)可視光線の中で一番波長が長い色は赤色で、一番波長が短い色は青紫です。太陽光には、全ての波長の可視光線が、ほぼ均等に含まれています。
私たちが普段見る光は、様々な波長の光が混じっています。 これを波長ごとに分けることを分光と言います。 ニュートンの実験も、分光を行っていることになります。 またこれ以上分光できない単一波長の光を単色光 といいます。
可視光線の波長の範囲は、一般的に380~780nmです。しかしその境界はかなりあいまいなので、 400nm~700nmとしても支障はありません。400~500nm、500~600nm、600~700nmと、三つの範 囲に分けて、波長の短い方から順に短波長、中波長、長波長と呼びます。長波長の光は主として 赤く、中波長の光は主として緑に、短波長の光は主として青く見えます。赤の光、緑の光、青の光、 この三色を「色光の三原色」と呼びます。
短波長 |
中波長 |
長波長 |
400~500nm |
500~600nm |
600~700nm |
青 |
緑 |
赤 |
なぜ光をプリズムに通すと分光するのでしょう?光は障害物 がないと直進しますが、物に当たると曲がります。光が曲がるこ とを屈折と言います。
また光は波長の長さによって、曲がる角度(屈折率)が 違います。波長が長いほど屈折率は小さく、波長が 短いほど屈折率は大きいです。各波長の光の屈折率のちがいによって、 光が分かれて、スペクトルが見えるのです。
雨上がりの空にかかる虹が見えるのも、空気中に浮遊している小さな雨粒が プリズムの役目をして、太陽光を分光しているためなのです。ハッキリ見えている虹 を主虹、うっすらと見えている虹を副虹と言います。
皆さん虹は何色ですか?私たち日本人は、7色 と教えられることが多いはずです。では6色はダメ なのでしょうか?5色は?2色は?
どれでも正解です。虹を見ると、虹の色の数は無限大と言っても良く 、決して「虹の色数は○色だ」とデジタルに決め付けることは できません。虹色は、アナログの世界なのです。だから15色と言っても間違いで はありませんし、2色と言っても間違いではないのです。虹の美しさを、 記憶にとめるため、私たちは虹の色を七色で表しているのです。

|
アフリカでは、虹の色は2色と考えている国もあります。熱い色と寒い色の 二色で成り立つんだ、と考えているのです。ちなみにスペクトルを発見した ニュートンは、スペクトル(虹)は7色に分けています。
私たち日本人とほぼ同じですね。しかしニュートンは、スペクトルを発見した当初 、スペクトルの色は6色に分割していました。藍色(インディゴブルー)がなか ったのです。ではなぜ7色になったのでしょう?
一つは「音楽の規則に合わせるため」です。 西洋では、色は音階のように何らかの規則性があると 考えられていました。階名は「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」 の七種類があります。そして和音は「ド・ミ・ソ」のように 規則性があります。音楽にも規則があるように、色にも 何らかの規則があるのでは?これを背景に、6色に 藍色が加わって、7色になったのです。
もう一つ、「7という数字は無難であるから。」です。 心理学で「青七現象」というのがあります。これは青と数字の7は、 文化に関係なく、どの民族からも好まれる確率が高い、という現象です。 「ラッキーセブン」「七五三」など、7を使った言葉は少なくありません。 しかも7は悪い意味で使われることはそんなにありません。
つまり7は、無難な数なのです。ニュートンが住んでいる場所は 、キリスト教がバリバリ盛んな地域です。6と言う数字は、「666」を連想して、 縁起が悪かったのかもしれません。666はキリスト教にとって、縁起の悪い数です。 (666の悪魔)ちなみに13も縁起が悪いです。日本では4と9ですね?逆に7や8 は縁起が良いですね。
太陽光は白色光です。太陽光は、全ての波長の光が、ほぼ均等に含まれているので、 無色に見えるのです。しかし白熱灯の色は、無色ではなくオレンジ色です。 白熱灯の光がオレンジっぽい理由は、赤やオレンジのような 長波長の光が、他の波長の光より多く含まれているからです。
蛍光灯の光は、黄や青の光が、他の色の光より多く含まれています。 最近では、白熱灯っぽい蛍光灯もあります。
白熱灯:赤みがプラスされる。
蛍光灯:青み&黄みがプラスされる。
可視光線以外にも、様々な種類の電磁波があります。 中でも「赤外線」「紫外線」はかなり有名です。 赤外線とは、赤の光よりも波長が長い電磁波です。赤外線は別名「熱線」 ともいわれ、コタツなどに利用されています。コタツの中は、 赤外線がいっぱいです。赤い光より外側の波長の光なので 、赤外線と呼ばれるのです。
紫外線は、紫の光よりも波長が短い電磁波です。 紫の光より、すぐ外側の電磁波なので、紫外線と呼ばれるのです。 DNAは、紫外線によって、比較的容易に破壊されます。そのため 紫外線は、少量なら殺菌効果があります。しかしあまりにも紫外線を 浴びすぎると、皮膚の具合が悪くなったり、ひどいときには 皮膚がんを起こす危険性もあります。
紫外線は殺菌や滅菌をするのに使われます。 化学実験や生物実験では、正確なデータを得るため、 周りの微生物を殺すシーンが結構あります。たとえば ヤクルト中の乳酸菌の数を知りたいとき、サンプル内 に他の微生物が入ると、正確に乳酸菌の数を数えるこ とはできません。例えば乳酸菌が入っているサンプルの一部を、 シャーレや試験管に移すとき、シャーレや試験管自体に雑菌が 含まれていたらアウトです。もちろん、乳酸菌を移す器具(薬さじなど) に雑菌が付いててもダメです。
雑菌を殺す手段として、紫外線ランプを使ったり、熱で殺した りなどがあります。試験管やシャーレを使うときは、 必要に応じて、滅菌したものを使います。ちなみに雑菌によって、 サンプルが台無しになることを、コンタミネーション(コンタミ) と言います。微生物はとてもデリケートです。実験は慎重に 行うべきです
話がそれてしまいました。紫外線は殺菌に有効です。 日干しをするのも、乾燥させるためだけでなく、紫外線によって、 微生物を殺すといった理由もあります。ただ紫外線は、色あせ の原因にもなるので、色ものを干すときは、長時間紫外線に さらさない方が良いです。
他にも様々な電磁波が、日常生活に活用されています。
レーザー波:航空機や船の探知、気象観測に用いられています。
Ⅹ線:レントゲンに活用されています。また分析機器にも使われています。
テレビ波:テレビの通信に使われています。
ラジオ波:ラジオの通信に使われています。
| SEO | [PR] おまとめローン 花 冷え性対策 坂本龍馬 | 動画掲示板 レンタルサーバー SEO | |
